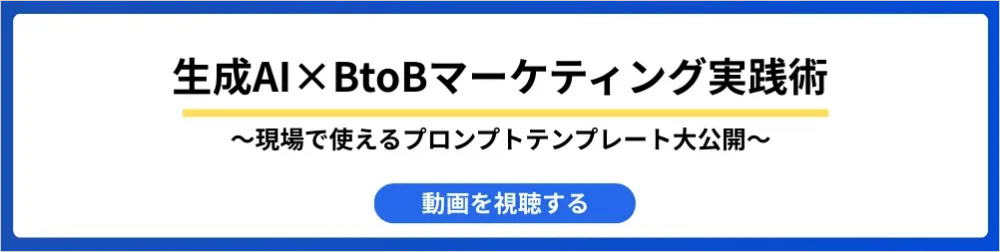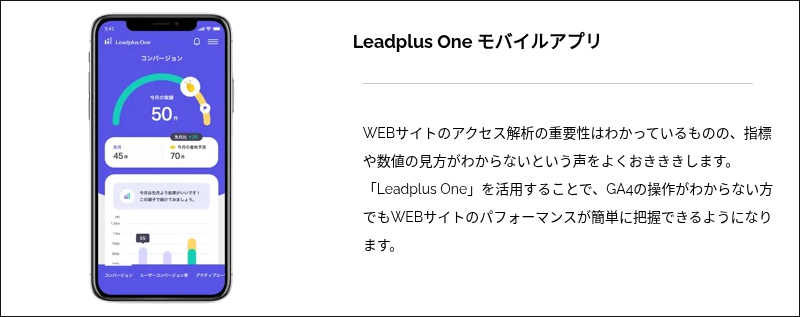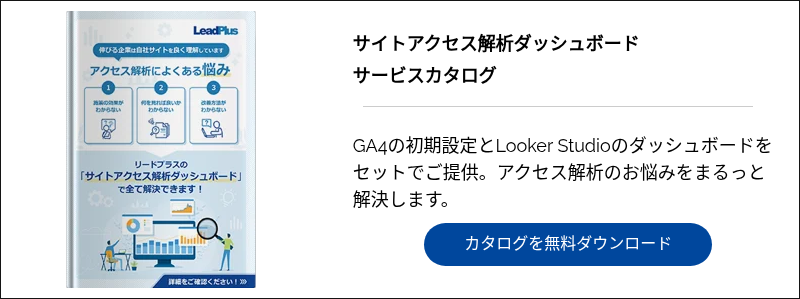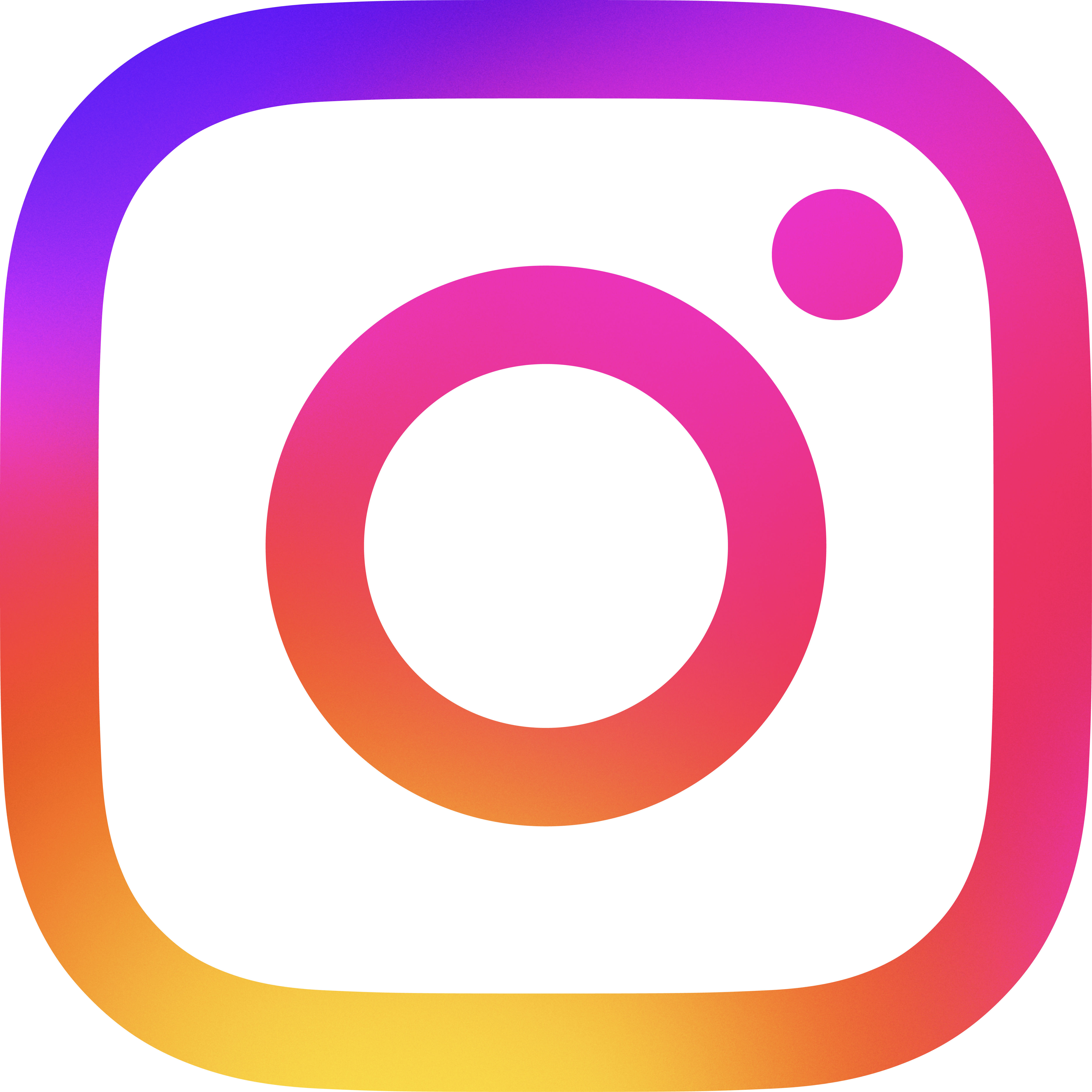なぜ、あなたの会社のマーケティングは成果が見えないのか?効果測定で始める経営改善
「意思決定をする上でデータが重要だとは分かっている。しかし、中小企業の限られたリソースで、専門家もいないのに一体何から始めれば…」。そう感じて、一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
データ分析と聞くと、難しく時間のかかるものに思えるかもしれません。本記事では、そんな多忙な経営者のために、完璧を目指さず「スモールスタート」で始められるマーケティング効果測定の方法を解説します。

なぜ今、経営に「マーケティングROI」の視点が不可欠なのか?
市場の変化が激しく、競合が多様化する現代において、「良い製品を作れば売れる」という時代は終わりを告げました。事業を成長軌道に乗せるためには、戦略的なマーケティング活動が不可欠です。しかし、多くの経営者が「マーケティングはコストがかかるばかりで、本当に売上に貢献しているのか分からない」という悩みを抱えているのではないでしょうか。
その課題を解決する鍵が「マーケティングROI」です。ROIとは「Return On Investment」の略で、投資した費用に対してどれだけの利益が生まれたかを示す「投資対効果」を測る指標を指します。この指標を正しく把握することで、マーケティングは単なるコスト部門から事業成長を牽引する投資部門へと変わります。そこで、勘や経験に頼る経営から脱却し、データに基づいた的確な経営判断を下すための具体的な手法を解説します。
「効果が見えない」が招く経営リスク|脱・どんぶり勘定マーケティング
マーケティングへの投資を「どんぶり勘定」で続けてしまうことは、単に非効率であるだけでなく、会社の未来を左右する重大な経営リスクにつながります。どの施策がどれだけの成果を生んでいるのかを把握しないままでは、貴重な経営資源を無駄に投下し続けることになりかねません。さらに、成果の基準が曖昧な状態は社内に無用な対立を生み、一丸となって目標へ向かうべき組織の力を削いでしまいます。
ここでは、効果が見えないマーケティング活動がもたらす具体的なリスクについて掘り下げていきます。
BtoB事業で費用対効果が見えないまま投資を続ける危険性
特にBtoB事業においては、顧客との接点が多く、検討期間が長期にわたるため、個々のマーケティング施策が最終的な受注にどう繋がったのかが見えにくくなりがちです。しかし、この費用対効果を曖昧にしたままでは、全く成果に結びついていない広告や展示会に、延々と予算を使い続けることになりかねません。
その一方で、データに基づき投資を最適化している競合は、より効率的に見込み客を獲得し、市場シェアを拡大していくことが可能になります。成果の不透明な活動への固執は、気づかないうちに自社の競争力を削ぎ、市場での存在感を低下させてしまう危険性があります。まずは自社のBtoBマーケティング活動の現状を直視し、費用対効果を測ることから始めましょう。
営業とマーケティングの対立を生む、曖昧な成果報告の弊害
「マーケティングは多くのリードを創出した」と報告するマーケティング部門と、「質の低いリードばかりでアポに繋がらない」と不満を漏らす営業部門。このような対立は、多くの企業で見られる光景ではないでしょうか。
この問題の根源は、両部門で「成果」の定義が共有されていない点にあります。マーケティングが、売上に直接つながらないアクセス数や問い合わせ件数といった中間指標のみを追い、営業が求める「受注見込みの高いリード」という最終ゴールと連携できていないのです。
このような社内の不協和音は、本来顧客に向けるべきエネルギーを内部で消費させるだけでなく、経営者にとっても頭の痛い問題となります。マーケティングの成果を売上への貢献度という共通言語で測る仕組みが、両者の連携を促し、組織全体の力を最大化させます。
中小企業が実践するマーケティング効果測定の3ステップ
「効果測定やデータ分析と聞くと、専門知識が必要で難しそうだ」と感じるかもしれません。しかし、ポイントを押さえれば、限られたリソースの中小企業でも、実践できるマーケティング効果測定の仕組みを構築できます。
大切なのは、最初から完璧を目指すのではなく、シンプルかつ重要な指標から着実に始めることです。ここでは、多忙な経営者でもすぐに理解し、実践に移せるよう、具体的な3つのステップに分けてその方法論を分かりやすく解説します。
ステップ1:経営者が握るべき最重要KPIの設定方法
まず取り組むべきは、自社のマーケティング活動を評価するための「ものさし」となるKPI(重要業績評価指標)の設定です。これは、目標達成に向けた進捗度を測るための具体的な指標を指します。
経営者は現場が追う細かい指標をすべて把握する必要はありません。抑えるべきは、事業インパクトに直結する数個の最重要KPIです。例えば、「有望な見込み客1件の獲得コスト(CPL: Cost Per Lead)」や「顧客1人の獲得コスト(CPA: Cost Per Acquisition)」、そして「顧客1人が生涯でもたらす利益(LTV: Lifetime Value)」などが挙げられます。
これらのマーケティングKPI設定を経営者自らが行うと、施策の評価基準が明確になり、報告も具体的になるでしょう。まずは自社にとっての「有望な見込み客」の定義を営業とすり合わせることから始めてみてください。
ステップ2:施策ごとの費用対効果を正しく算出する
KPIを設定したら、次は各マーケティング施策の費用対効果を具体的に算出します。計算式はシンプルで、「(施策による売上や利益 - 施策コスト)÷ 施策コスト × 100(%)」でROIを求めます。
例えば、100万円かけた展示会から500万円の受注が生まれた場合、ROIは400%です。Web広告やWebサイトからの問い合わせといったオンライン施策はツールで比較的簡単に計測できます。一方、オフライン施策の場合は、アンケートで「当社を何で知りましたか?」と質問するなど、地道な確認作業が有効です。全ての施策を一度に計測するのは労力がかかるため、まずは予算の大きい施策から費用対効果を試算してみるのが現実的なアプローチと言えます。
ステップ3:散らばったデータを経営判断に活かす管理術
各施策の費用対効果が見えてきても、そのデータがバラバラに保管されていては、次の経営判断に活かせません。Web広告の管理画面、Webサイトのアクセス解析データ、営業部門が使うSFA(Sales Force Automation/営業支援ツール)やExcelの顧客リストなど、散らばった情報を一元的に管理する仕組みが必要です。
最初から高価なツールを導入する必要はなく、まずは各担当者から主要な数値を集約する共有スプレッドシートを作成し、月次で更新するルールを定めるだけでも大きな一歩となります。重要なのは、データを一箇所に集めて全体像を俯瞰できるようにすることです。これにより、どの施策が好調でどこに課題があるのかが一目瞭然になり、データに基づいた次のアクションを検討できます。
データドリブンな意思決定を組織に根付かせるには
データを集め、分析する仕組みを整えるだけでは、データドリブンな組織への変革は達成できません。最も重要なのは、そのデータを基に考え、行動する文化を組織全体に根付かせる点にあります。これには、経営者自らが旗振り役となり、粘り強く取り組む姿勢が求められるでしょう。
ここでは、分析結果を単なるレポートで終わらせず、日々の業務や戦略に活かし、組織の血肉とするための具体的な方法について解説します。
全社の目線を合わせるための目標共有と会議体設計
データドリブンな文化を醸成する第一歩は、経営者と現場の視座を合わせることです。会社の最終的な売上や利益目標を明確に示し、その達成のためにマーケティング部門がどのようなKPIを追うのかを全社で共有しましょう。
その上で、営業とマーケティングの担当者が定期的に集まり、数字を基に進捗を確認し、課題を議論する会議の場を設けることが極めて重要となります。この会議では個人の責任を追及するのではなく、あくまで「数字という事実」を基に「次はどうすればもっと良くなるか」を建設的に話し合う場にすることが成功の鍵です。経営者も参加し、データに基づいた意思決定を自ら実践する姿を見せることで、組織全体の意識は変わっていきます。
小さく始めて大きく育てる、効果測定の習慣化
いきなり全てのマーケティング活動を完璧に測定しようとすると、その負荷の大きさから挫折してしまいがちです。まずは、最も予算をかけている施策や、成果が見えやすいWebサイト経由の問い合わせなど、一つか二つのチャネル(施策や媒体)に絞って効果測定を始めることをお勧めします。
そして、その小さな成功体験を社内で共有し、「やれば成果が見える」という手応えを関係者に感じてもらうことが大切です。一つの施策で効果測定のサイクルを回せるようになれば、その経験を他の施策にも横展開していくのは比較的容易でしょう。焦らず着実に測定の範囲を広げていくことで、組織に「数字で語る」文化が無理なく浸透し、習慣化していきます。
マーケティングROI経営を加速させる具体的ツールという選択肢
これまで解説してきた効果測定やデータ管理は、手作業でも始めることが可能です。しかし、事業の成長とともに施策が複雑化してくると、手作業では限界が見えてくるのも事実でしょう。
そこで選択肢となるのが、マーケティング活動を効率化し、分析を高度化するための各種ツールです。ツールはあくまで手段であるものの、うまく活用するとデータ収集や分析にかかる時間を大幅に短縮し、より本質的な「考える時間」「意思決定する時間」を生み出します。ここでは、マーケティングROI経営の実現を力強く後押しする具体的なツールを紹介します。
HubSpotで見える化する、オンラインの顧客接点と投資対効果
HubSpotは、世界中で広く利用されているCRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)プラットフォームです。その最大の強みは、顧客情報を管理するCRMを土台に、マーケティング、営業、カスタマーサービスの機能が統合されている点にあります。これにより、顧客が初めてWebサイトを訪問してから受注に至るまでの一連のプロセスが、一つのシステム上で可視化されます。
どのマーケティング活動が有望な見込み客を生み、最終的にいくらの売上につながったのかが明確になるため、施策ごとの正確なマーケティングROIの算出が格段に容易です。中小企業でも導入しやすい価格プランが用意されているのも魅力と言えます。
なお、HubSpotプラチナパートナーのリードプラスでは、HubSpot導入・運用支援サービスを提供しています。
LeadplusOneで次に打つべき一手が見える、シンプルなアクセス解析
「高機能なツールは難しそうで、使いこなせる自信がない」と感じる経営者の方も少なくないでしょう。そんな場合に有効なのが、シンプルさと分かりやすさに特化したツールです。
例えば「LeadplusOne」のようなサービスは、Webサイトを訪れた企業名がわかるアクセス解析機能を持ちながら、専門家でなくても直感的に扱えるように設計されています。単にデータを示すだけでなく、そのデータを基に「次にどんなマーケティング施策を執るべきか」を分かりやすく提示してくれるため、分析から具体的なアクションへの橋渡しをスムーズに行えます。
まずはこのようなシンプルなツールから始め、データを見て次の手を考える習慣をつけることが、データドリブン経営への確かな一歩です。
データに基づいた意思決定で未来を創るための第一歩
本記事で紹介した手法やツールは、あくまで経営判断の精度を高めるための道具です。最終的に未来を創るのは、データを読み解き、リスクを取って決断を下す経営者自身に他なりません。
重要なのは、完璧なデータ分析を待つのではなく、今ある不完全なデータの中からでもより良い選択肢を見つけ出そうと努める姿勢です。まずは、最も気になる一つの施策の費用対効果を概算してみる、あるいは営業とマーケティングの合同会議を一度開いてみるといった、小さな一歩から始めてみてください。
その一歩が、勘と経験だけに頼った経営から脱却し、データという強力な武器を手に、会社の未来を切り拓くための始まりとなるでしょう。